大石静さん脚本のℕHK大河ドラマ、「光る君へ」を作家Aは興味を持ってみているところです。平安時代の伝達方法は、限られた階級の人達だったとはいえ、美しいかな文字と漢文。我々はSNS時代。人と人との交わりの濃い情の表現が、紙文化に深く根差していることに改めて気づかされています。

大石静さん脚本のℕHK大河ドラマ、「光る君へ」を作家Aは興味を持ってみているところです。平安時代の伝達方法は、限られた階級の人達だったとはいえ、美しいかな文字と漢文。我々はSNS時代。人と人との交わりの濃い情の表現が、紙文化に深く根差していることに改めて気づかされています。

創ることが生活になっている作家Aにとって、新聞の「声」欄を読むたび教えられることが多いように思います。中学三年生の国語の試験問題、「フィルターバブル現象」という言葉について知ったことも、私には今の世情を識る一助になっています。


我庭のエビネランの群生、今年は花つきが悪く気候のせいかと案じられ、山を歩いてみました。白い卯の花が咲き乱れ、ホタルブクロの色どりを目にして清々しい空気にほっとしたところです。
「野の恵み」


端午の節句です。
此度の仔象、響きは女の子です。
五月の風が感じられるでしょうか。
山中から出かける作家Aにとって松山の店で出会うお客様方との語らいは新鮮です。
先頃は犬好きの共通話題だったのですが、愛知県のS様から犬香合のご依頼を受けることになりました。作る方も思いがけないご依頼なのでどんな表現になるか楽しみです。


「響き」シリーズの仔象に作家Bが名前をつけました。イタリアの路地裏で中世の古書を売っている本屋のカウンターに鎮座していそうだとか。仔象なのに貫禄があるそうです。近日中に松山の店で飾る予定です。
創る時間が余り残されていない作家Aです。作品の新しいテーマ創りを探っています。長い間還元炎中心に焼成。此の頃練り込みの色彩を黄色で試み始め、酸化炎焼成しています。そんな折東京、銀座で個展を続けていた頃、何度か近くで個展を催されていた高木慶子さんから三冊目の画集が届きました。大学の先輩のがんばりに背中を押されたようです。
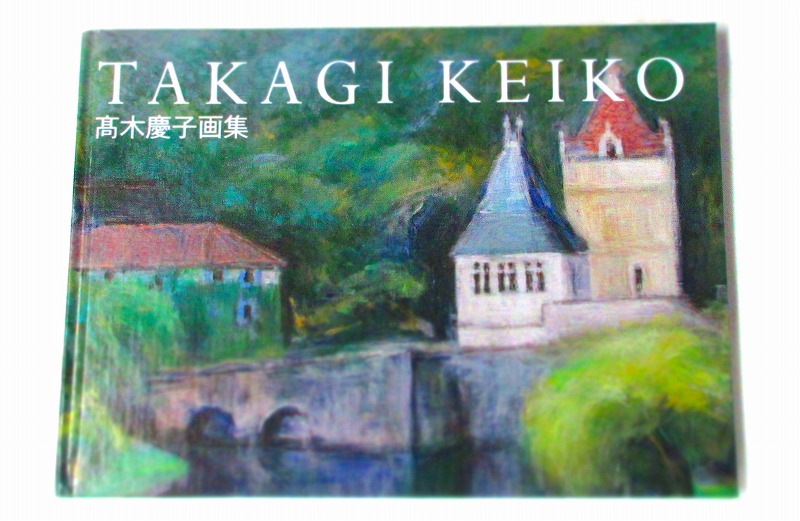
島から今治へは一時間に一本のバスです。待ち時間、岩波書店の「図書」を携えています。「図書」は一年間1000円の定期購読、現在「図書」で執筆中の大学時代の同級生から送られ、定期購読を開始。表紙を飾るのは去年まで、現代美術作家の杉本博司氏で、マダムタッソー蝋人形館の人形の写真でした。裏面に解説があり、それが時代背景と共に深く広く魅力的でした。今年は購読延長は如何にと思っていたのですが、小児科医師の加藤清允氏、表絵の絵も裏面の解説も楽しく購読を続けることにしました。バスを待つ時間が充実しそうです。


我が窯の庭では満月蠟梅をめでる睦月です。
能登半島地震、元旦からきびしい時間が流れています。
自然災害の中にある日本、がんばりたいものです。
何時も干支の準備をする時、特に続いているこの不安定な時勢、少しでも平安な年になる様願いを込めます。来年は甲辰の年、調べてみると甲は十干のスタートであり樹木の成長、辰は天に向かって飛翔するイメージとあります。縁起のよい年のようです。
今年最後の龍を焼き上げました。

